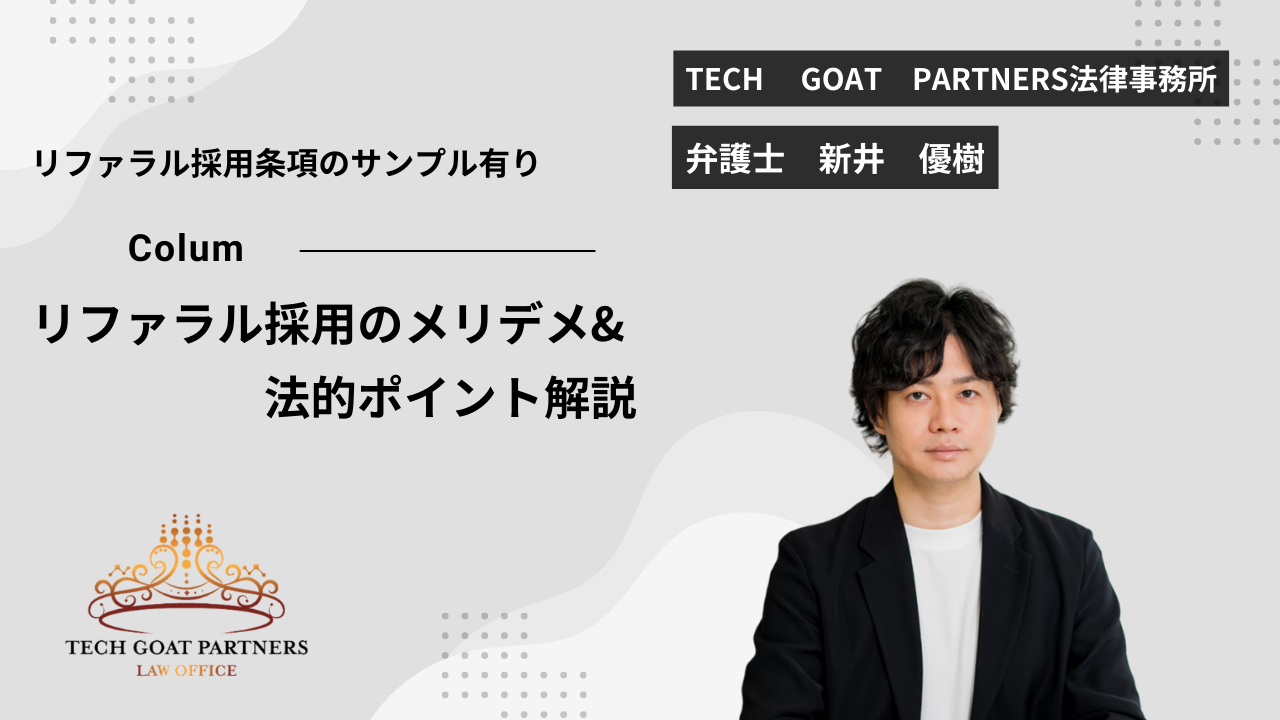【弁護士執筆&契約書条文例有り】著作権の譲渡に関する契約書の条文例と注意事項

1 著作権者と著作権の利用
(1) 「著作権者」とは
著作権はその著作物を「創作した人」に帰属します。そのため、著作物の制作を外注した場合には、受注者にその著作物の著作権が帰属します。例えば、Webサイトのデザインを外部のイラストレーターした場合には、制作物の制作料金を支払ったからといって当然に著作権が自社に移転することにはならないので注意が必要です。
(2) 著作物の利用
著作権者以外の人が著作物を利用する場合には、①権利制限規定に従って利用するか、②著作権者の同意を取得する必要があります。
①権利制限規定の詳細は別の記事にして解説予定です。
著作権の譲渡を受けなかった場合には、その著作物を自由に利用することができないことに注意が必要です。
2 著作権の譲渡が必要なるケース
BtoBの取引において著作権の譲渡が必要になるケースは多いです。というのも、一度納品を受けた制作物を発注者において修正をしたり、別のイラストレーターやベンダーに共有して修正をすることがあり得るためです。その際に、著作権の譲渡を受けるか利用許諾を取得していないとそれらが実行できない可能性があることに注意が必要です。
- フリーランスのイラストレーターにHPのデザイン制作を依頼するケース
- システム開発会社に自社オリジナルの受発注管理システムの開発を委託するケース
3 著作権譲渡に関する著作権法のルール
(1) 著作権の譲渡
前述した通り、著作権は「創作した人」に帰属するため、著作権の譲渡に関する合意をしない限り発注者や第三者に移転しません。
そのため、発注者において著作物の利用が必要な場合には、受注者との間で著作権の譲渡に関する合意をする必要があります。
(2) 著作権の譲渡に関する特別なルール
著作権の譲渡に関しては、一般の権利の譲渡は異なる特別なルールが存在する。
それは、著作権のうち、著作権法第27条に定める権利と第28条に定める権利については「特掲」しなければ著作権者に権利が留保されたものと推定されてしまうというものです(著作権法第61条2項)。
「特掲」したと評価されるようにするために、契約書上でこれらの権利が譲渡対象になっていることを明確にするのが実務上の一般的な処理です。具体的な契約書条項例は本記事の後半に記載しています。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(3) 著作者人格権の不行使
著作権の譲渡を受ける際に忘れてはいけないのが著作者人格権です。
著作者人格権はその著作物を創作した人に帰属する権利の中で譲渡不可能な性質(一身専属権)を持つため、譲渡対象にすることはできません。
譲渡できないからといって契約書上何ら手当をしないと、著作者人格権を行使されてしまう可能性があります。
そのため、著作者人格権の不行使を誓約させることが一般的です。
4 著作権譲渡と独禁法・下請法
著作権の譲渡を伴う取引を行う場合には独禁法・下請法に違反しないように注意する必要があります。
特に以下の様な場合には、優越的地位の濫用やかいたたきに該当する可能性があります。
- 権利譲渡の対価が不当に低い場合
- 権利譲渡を事実上強制したような場合
この点に関しては、総務省が公開する資料において、独禁法・下請法との関係で問題となり得るケースが紹介されているため、自社の発注がこれらに該当していないか確認してみましょう。
5 著作権譲渡の契約書条項例
(1) 受注者に留保する場合
成果物に関する著作権を受注者に留保する場合には下記のような文言にすることが考えられます。受注者に権利留保されることで発注者が成果物を自由に利用できなくなるため、この規定で発注者において問題が生じないのはPoC契約等に限定されます。
成果物に関する著作権は受注者に留保されるものとする。
実務上、成果物の利用をする前提で発注することが多いので、成果物の利用に必要な範囲での利用許諾を付けることが一般的です。なお、利用許諾の範囲に疑義が生じないように、その範囲については詳細な定めを置くことが望ましいです。
成果物に関する著作権は受注者に留保されるものとする。ただし、受注者は発注者に対して、当該成果物に利用に必要な範囲[〇〇に関する利用に必要な範囲]でその利用を許諾する。
(2) 発注者に譲渡する場合
発注者としては、成果物の著作権の譲渡を受けておくと、その後の利用や修正を自由に行うことができます。
1 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、検収完了時点受注者から発注者に譲渡されるものとする。ただし、本契約締結以前から受注者がその権利を保有する著作物にかかる著作権は受注者に留保されるものとする。
2 受注者は発注者に対し、前項ただしがきに記載する著作権に関し、成果物の利用に必要な範囲においてその利用を許諾する。
発注以前から受注者に帰属する著作権については、受注者に留保させつつも成果物の利用に必要な範囲で利用許諾を取得することを忘れないようにしましょう。
なお、実務上は、発注者に権利が移転する著作物の範囲と受注者に帰属する著作物の範囲が明確に区別されていない事例が散見されます。制作物の性質にもよりますが、これらの範囲は明確にしていない場合には、後日、紛争の対象が発生し得る点に注意が必要です。
TECH GOAT PARTNERS法律事務所では、Webサイト制作やシステム開発契約書等の著作権の帰属に関する定めの重要性が高い契約書の作成・レビューをご依頼いただいております。著作権を一度不適切に処理してしまうと事後的な対応が必要になってしまうため、ビジネスを始める最初のタイミングでご相談ください。また、既に不適切な処理をしてしまってお困りの会社様も事後的な対応にてケアすることが可能なケースもありますので、お気軽にご相談ください。
初回の無料面談はこちらからお申し込みください。