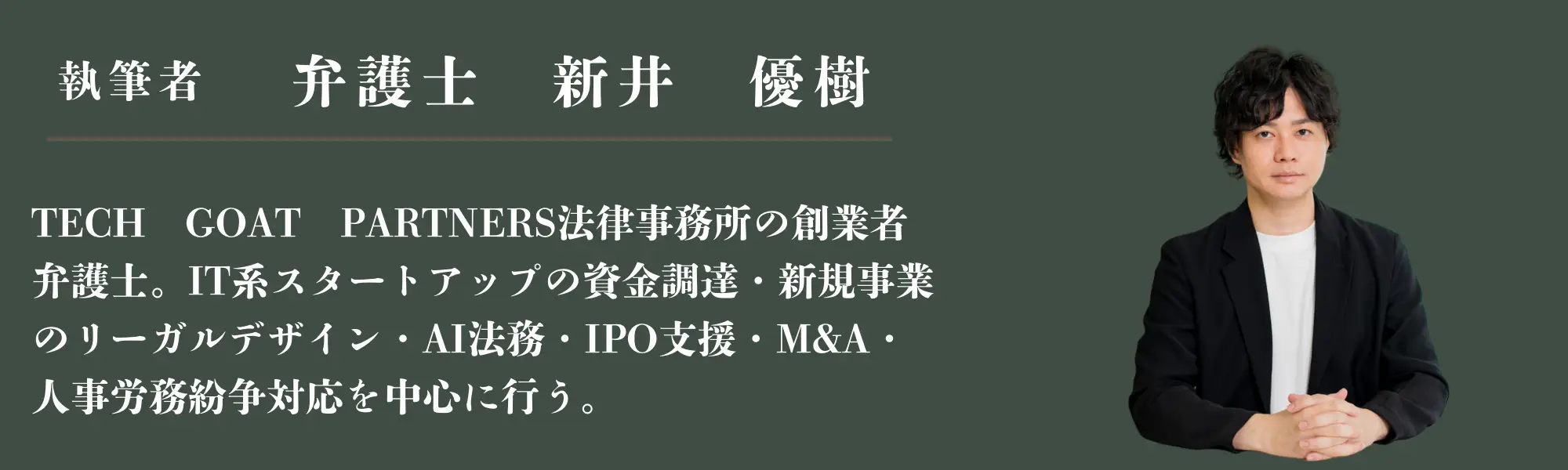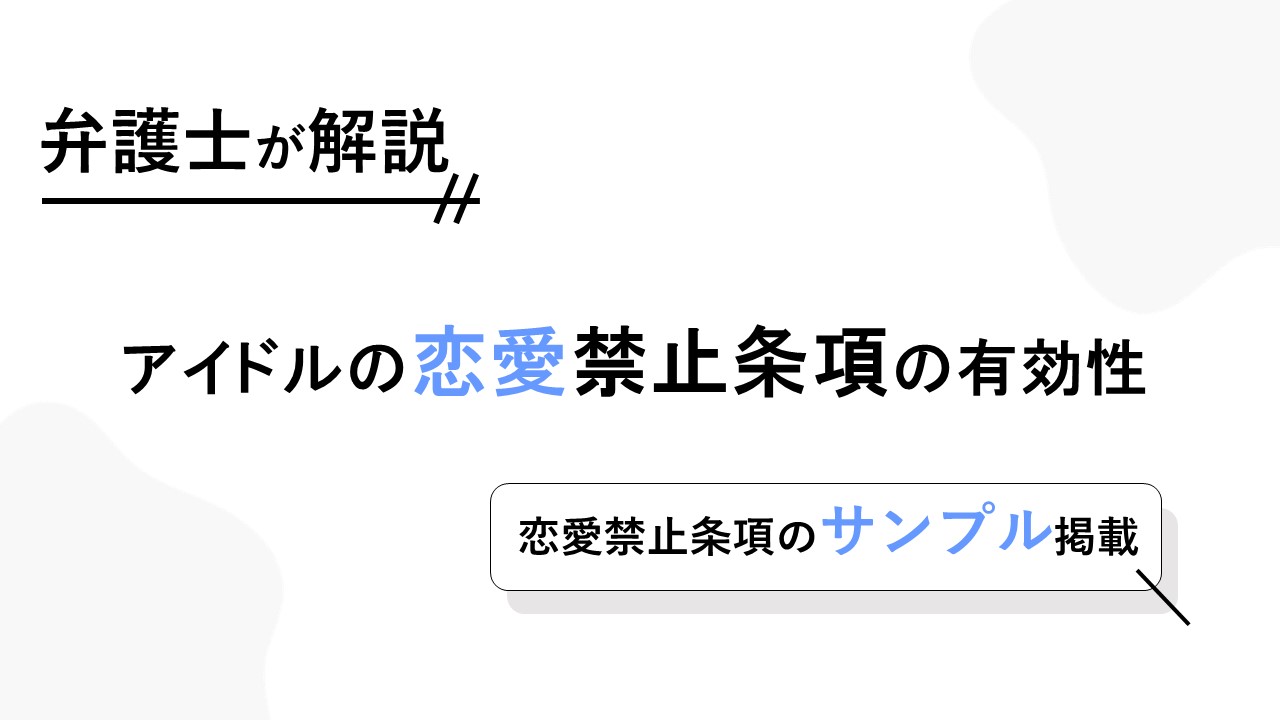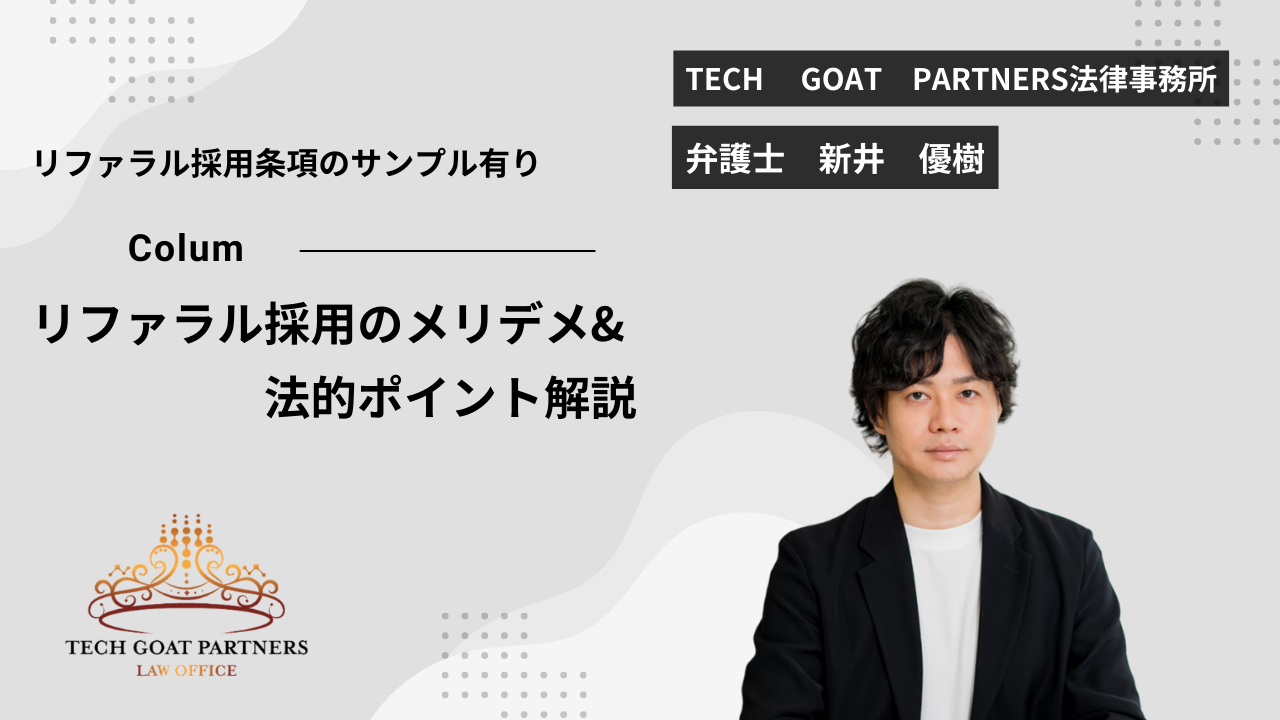【弁護士執筆】芸能プロダクションに所属するタレントのSNSアカウント運用方法

1 はじめに
芸能プロダクションに所属しているタレントがSNS活動を行う場合、芸能プロダクション側でSNSのアカウントを管理・運用することがあります。昨今、SNSは良い意味でも悪い意味でもタレントのプロモーション活動には非常に重要な役割を果たしています。タレント自身がSNSで直接発信することでファンが親近感を感じ、よりエンゲージメントを高めることができる一方で、不用意な発言によって炎上し、ファン離れを引き起こしてしまうことも珍しくありません。本記事では、芸能プロダクションに所属するタレントのSNSの管理・運用方法について解説します。芸能プロダクションとしてどのような内容をタレントと協議すべきかを確認してみましょう。
2 SNSの管理・運用権者
(1)SNSの管理・運用方法
SNSの管理法としては、①タレント個人が管理する方法、①芸能プロダクションのみが管理する方法、③タレントと芸能プロダクションにて共同管理する方法が考えられます。それぞれのメリット・デメリットを解説します。
(2)①タレント個人が管理する方法
(メリット)
- タレントが好きな時に好きな内容を発信できるので自分らしさを発揮しやすい
- ファンがより親近感を感じやすい
- 芸能プロダクションの管理コストが発生しない
(デメリット)
- 炎上し得る内容を発信した際に芸能プロダクションが削除や修正のコントロールが出来ない
(3)②芸能プロダクションのみが管理する方法
(メリット)
- 発信内容を芸能プロダクション側で全てコントロールできるのでタレント本人による不用意な発信を防止できる
(デメリット)
- 発信内容がイベントなどの出演情報告知やスタッフが撮影した写真・動画のupが多くなるため事務的な雰囲気が強く成り親近感がわきにく
(4)③タレントと芸能プロダクションにて共同管理する方法
(メリット)
- タレントが芸能プロダクションとの間で決めた一定のルールの下で自由に発信出来る
- 基本的にはタレント発信なのでファンも親近感を抱きやすい
(デメリット)
- タレントと芸能プロダクションのSNS運用方針に相違がある場合には関係値が悪化する要因となる
- 芸能プロダクションのSNS運用方針に不満を持つタレントが芸能プロダクションには知らせずに裏垢を運用し始める可能性がある
(5)まとめ
SNS上のリピテーションはタレントの価値に直結するため、炎上防止の観点から①タレント個人のみに任せる運用形態は非常にリスクの高い方法です。②芸能プロダクションのみが管理することで炎上リスクは相当程度抑えることが出来ますが、タレントとの親近感という意味では劣ってしまい、ファンにとっての楽しみを大きく減少させてしまします。そのため、SNS運用は③タレントと芸能プロダクションの共同運用とすることが望ましいものと考えられます。
3 SNSの運用ルール
(1)はじめに
タレントと芸能プロダクションが共同でSNSを運用する場合、SNSの運用に関するルールを契約書等で定めておく必要があります。契約書には様々な事項が記載されており、SNSの運用に関するルールが目立ちにくい側面もあるため、「SNS運用に関するルールブック」といった形で契約書からSNS運用に関するルールを抜き出したものを別途作成する方法もおすすめです。
では、SNSの運用に関してどのようなルールを定めておく必要があるのでしょうか。
(2)SNSの運用ルールとして定めておくべき内容
SNSの運用ルールとしては以下の内容を定めておくことが望ましいです。以下、それぞれについて解説します。
- ①SNSのログイン情報の共有
- ②SNSの発信内容
- ③SNSでのフォロー/フォローバック
- ④SNSへのコメントへの対応
- ⑤SNSのDM対応
- ⑥契約終了後のSNSアカウントの取扱い
(3)①SNSのログイン情報の共有
SNSのログイン情報としては、ID・パスワード・電話番号・メールアドレス等が必要になることが一般的です。
タレントが炎上リスクのある内容を発信してしまったり、情報解禁前の情報を誤って公開してしまったような場合には直ちに発信内容の修正・削除・謝罪対応に動く必要があります。
タレント本人が自分で気づいて対応できれば良いですが、タレント本人には不適切な内容を発信した自覚が無いケースもあるので、芸能プロダクション側で直ちに対応に動ける体制にする必要があります。そのためには、SNSのログイン情報を芸能プロダクション側で管理しておくことが必要となります。
なお、ログイン情報は定期的に確認し、勝手にログイン情報が変更されていないかの確認をすることを忘れないように注意しましょう。
(4)②SNSの発信内容
SNSの発信は良くも悪くも瞬時に拡散されてしまいます。
特に炎上リスクのある発言はすさまじい速度で拡散されることも多いため、炎上リスクの高い発言については事前に禁止事項または芸能プロダクションの承認を得る事項として設定することが望ましいです。例えば、以下のような発信には注意が必要です。
- 政治的な発言
- 暴力的な発言
- 性自認等に関する発言
- 競合他社に関する発信
- 第三者の名誉・信用を毀損し得る発信
また、タレントに対してSNSの運用に関する研修会を実施し、炎上リスクのある発信内容について具体的な例を挙げて定期的に注意喚起することも良いでしょう。
(5)③SNSでのフォロー/フォローバック
タレントのSNSアカウントのフォロワーは基本的にはタレントのファンです。
ファンとしては、タレントが誰をフォローしているのかは気になるところです。タレントの交友関係を推測できるものでもあるからです。
フォロー基準の設定は悩ましい所ですが、フォローに関しては同じ事務所の関係者に限定するなどしてファンに無用な憶測を生まないようにするのも良いでしょう。特に異性のアカウントをフォローする場合には、関係性を疑われることを意識することが必要です。
フォローバックについても同様に悩ましい所ですが、ファンに対するフォローバックは全て行うor一切行わないの二択にしてしまった方が良いです。というのも、フォローバックの有無でファンの中での区別が生まれてしまうからです。ファンの中に序列があるかのように見える運用は控えることが望ましいです。
(6)④SNSへのコメントへの対応
SNSのアカウントに対するコメントへの対応については、①個別に返信する、②「いいね」のリアクションのみを付ける、③反応しないといった選択肢が考えられます。
①個別に返信することでファンにとっては非常に嬉しいものですが、返信がしにくい内容もあるため、運用の難易度が高く、コメント量が多い場合には工数も重いものとなります。
②「いいね」のリアクションのみを付ける方法であれば、ファンとのコミュニケーションとしてはやや劣るものの、「コメントを読んでいる」ことは最低限伝えられます。また、対応工数はそこまで重くはなりません。
③一切反応しないという選択肢は工数のみを考えると非常に楽ではあり、リアクションが全員に対して無いという意味では平等です。もっとも、ファンが少ない初期段階においては、ファンのエンゲージメントを高めきれずに離脱を誘発するリスクがある点に注意が必要です。
(7)⑤SNSのDM対応
SNSのDMはファンとの繋がりを誘発する最大のリスクであることに十分注意が必要です。
また、コメント以上にファンとの距離が近いため、DMの返信の有無や内容でファンの中での区別がより生まれやすいところです。
一方的に送信されてしまうものはやむを得ない部分がありますが、DMの返信内容を適切にコントロールできる体制が構築できない限りは、基本的には反応しない選択肢を取ることが無難であるといえます。
(8)⑥契約終了後のSNSアカウントの取扱い
SNSアカウントについては、①タレントが芸能プロダクションに所属してからSNSアカウントを作成する方法と②芸能プロダクションに所属する前からタレント本人が運用していたSNSアカウントを流用する方法の二つのパターンが考えられます。
①の場合には契約終了時にタレントのアクセス権限をブロックすることで問題はありませんが、②の場合には、元々タレント個人のアカウントであるため芸能プロダクション側で削除等を行うのは不適切であり、タレントも納得できないところです。
②の場合には、契約終了時に発信する内容、過去の発信で削除すべき内容等を芸能プロダクションとタレント側で協議し、それらの対応が完了した時点で芸能プロダクションのアクセス権限をタレント側でブロックしてもらうことが望ましいです。
4 まとめ
本記事で解説している内容はタレントと芸能プロダクションとの間で合意すべき基本的な事項に留まります。実際には、契約書等でかなり細かく設定すべき事項が存在するため、案件毎に適切な内容をアレンジしていくことが必要です。
TECH GOAT PARTNERS法律事務所では、芸能プロダクション側をサポートする弁護士として、タレントとの契約内容のアレンジ・契約書の作成・オペレーションの構築までを一気通貫で対応しております。タレントとの契約内容や管理に関するオペレーションでお悩みの方は、まずはこちらから無料面談をご利用ください。